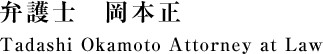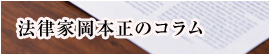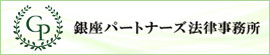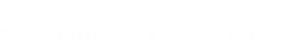【コラム】三宅島の皆様との意見交換~平野祐康 元三宅村長・三宅島観光協会・ギャラリーカフェカノン
2025年5月17日から5月18日にかけて、日本災害復興学会復興支援委員会のメンバーらとともに三宅島に滞在。元村長、観光協会、そして島民の皆様、その他多くの方々からお話を伺いました。私の考えたことを速報で備忘メモにしておきます(未定稿)。
(5月17日)
元・三宅村長で防災アドバイザーの平野祐康氏と、三宅島観光協会事務局長の谷井重夫氏のレクチャーを受け、意見交換を実施しました。
谷井(やつい)氏からは三宅島の観光の現在と未来について教えていただきました。三宅島の溶岩台地の景観を生かした「ロケーション・ツーリズム」や、離島ならではの「スペシャル・インタレスト・ツーリズム」によるインバウンド需要等に手ごたえを感じることができました。
平野元村長からは、2000年の三宅島噴火災害に伴う三宅村の主な対応や施策について、災害時、避難中、帰島後について幅広くお話を伺い、また意見交換をすることができました。なぜ全島避難後速やかに95%以上もの避難者の居所を把握できたのか?なぜ多くの島民がバラバラに避難しながらも4年半後に多くの島民が帰島を果たすことができたのか?既存の制度の限界をどうやって克服したのか。どうやって新しい支援を引き出すことができたのか。非常に示唆に富むお話しでした。
当時は被災者生活再建支援金も現在ほど使い勝手はよくありませんでした。そこで東京都が追加の独自支援を行うなど上乗せや横出しの支援を展開しています。自治体による法の間隙を埋める特別措置の先駆けであろうと考えられます。
生活再建資金を手元に残す必要がある一方、それにより所得や資産が大きくなることで支援を受けられなくなるという弊害を克服すべく、別枠で再建資金を確保しつつ、日常生活資金は別途支援されるような特例制度も作りました。これは2011年以降の被災ローン減免制度(個人版私的整理ガイドライン、自然災害債務整理ガイドライン)で現預金500万円は別枠で残せるというしくみと同質だと言えます。
様々な公的貸付制度は、結局は返済不能で焦げ付き、いまだに自治体でいわゆる不良債権として残っていることもわかりました。同様の課題はコロナ禍での緊急貸付制度で多くの債務者でもおきています。
三宅島の施策から良施策や復興政策の課題をもう一度学びなおし、何が課題として残り続けているのかを改めて明確にしておくこと必要であると実感しています。今後とも日本災害復興学会で研究を継続する予定です。
(5月18日)
ギャラリーカフェ「カノン」にて、画家の穴原甲一郎先生、平野奈都さん(地域体験工房しまのね・自然ガイド・雄山火山体験入山775ツアーなど実施)の親子から、島民目線のリアルな避難生活当時の話を伺うこともできました。カフェカノンの壁面は穴原先生の美しい精緻な三宅島の風景の絵画が飾られています。
穴原先生は、当時三宅島の学校の先生。平野さんは当時三宅島の中学生。2000年三宅島噴火と先行した子供たちだけの東京への避難の状況などを伺うことができました。予測できない将来のなかで子供たちが晒されてしまった過酷な状況。「いつどうなるかわからない」という不安は、精神的・肉体的な健康をどんどんと蝕んでいきました。当時の集団生活や避難生活の写真、学童疎開先になった全寮制の秋川高校での困難な生活、忘れてはならない教訓を伺うことができました。子供たちは、「設備や場所的環境」によって学習機会が大幅に失われるということは実はなく、どんな環境下でも最低限の教材さえ提供できるのではないか。もっとも失ってはいけないのは学校の教室の授業ではなく、「居場所」である家族と一緒の生活だったのではないか。
「いつどうなるのかわからない」「いつまで避難生活が続くのか」「家族が離れ離れになってはいけない」。この漠然とした、しかし確かに存在する将来への不安が精神的・肉体的健康を毀損させていく。これは三宅島の噴火以降も、多くの災害で観察されてきました。福島原子力発電所事故、甚大な津波被害を受けた東日本大震災の被災地、長期インフラ不通や複合災害で生活再建のめどが立たない能登半島地震・奥能登豪雨の被災地等に三宅島での教訓を伝えきれていなかったのではないかと反省する次第です。
たとえば能登半島地震の広域避難(2次避難)の際には、避難先(たとえばみなし避難所となった宿泊施設やホテル等)では、男女別になってしまい、夫婦が分離してしまい、介護介助ができなくなることも起きています(本来は要介護状態でも夫婦生活や親子生活のなかで特に要介護者の認定を受けていないケースは多数あります)。また、他人と急に同部屋で就寝しなければならなくなり、強いストレスになってしまった方もいます。親子、夫婦、同居家族を分離させない、そして家族のプライベートを確保できる避難を徹底すべきだと実感しました。災害救助法の特別基準等による支援メニューも、そのような点に注力して実践されるべきではないでしょうか。
避難生活者への支援は、物資もありがたいですが、何に変えても現金支援が一番だということも再確認しました。生活必需品は避難先であれば確実に購入できます。支援は現物ではなく現金が最も効率的で効果的なのです。災害救助法は現金支給ができると定めていますので、この条項を活用することが知事や首長の責務です。例えばその後の能登半島地震では、奥能登から金沢市に1.5次避難や2次避難してきた方へ食費相当の現金支援を模索していました。金沢市は、災害救助法の予算による施策実施を強く希望し、国や石川県へ要望しました。しかし、石川県や内閣府が反対し実現に至らず、結果として金沢市の予算でクオカードを配布するにとどまったのです。法整備以前に、現行法の活用もまだまだ課題が残ります。
三宅島ならではの防災教育ができるのではないか。三宅島は風雨によって三宅島は3つある港を毎日使い分けます。フェリーがどこに寄港するかは、三宅島に近づいてから決まるのです。噴火災害に備えるという意味でも「風」を読むことは重要です。子供たちは常に風を体感しながら暮らしています。風、雨、台風などを中心に防災教育を行うことで、本土での防災教育ができるだけの人材育成ができるのではないかと思います。三宅島には高校まであります。気象予報士取得を目指す子供たちが増えても面白いかもしれません。