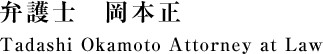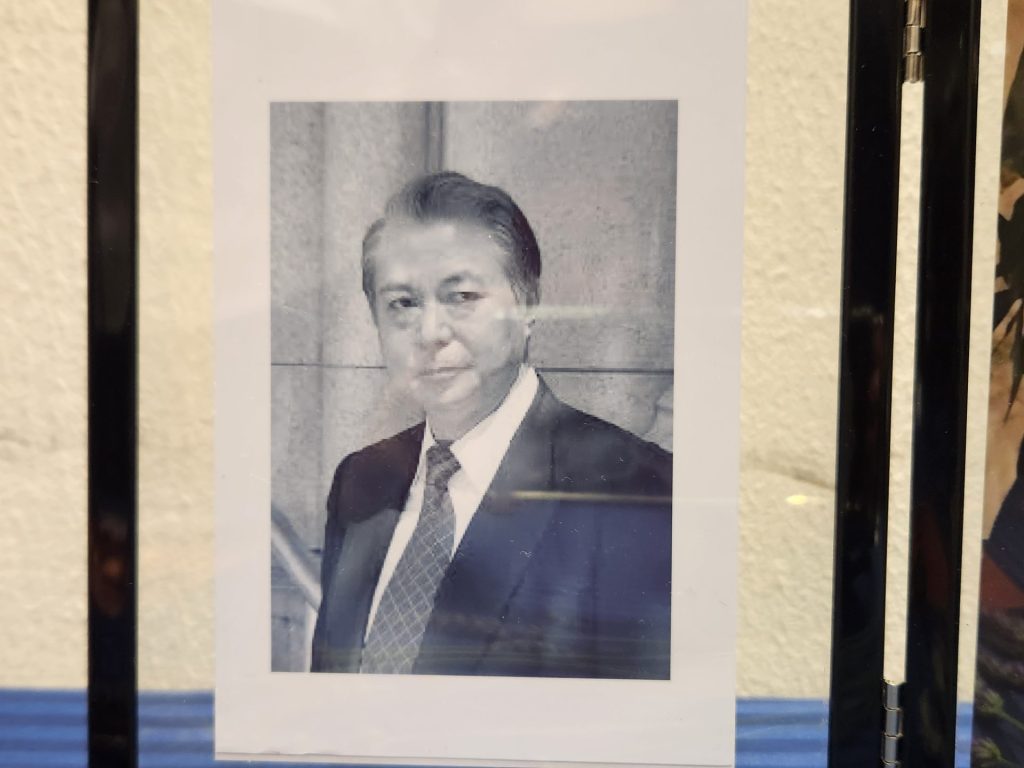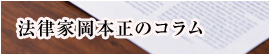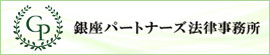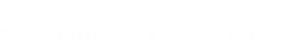恩師平良木登規男先生へ
2025年(令和7年)1月8日、大学のゼミの恩師である平良木登規男先生が亡くなられました。
82歳という御年齢は、平良木先生を知る私たちからしたら信じられないほど早すぎる年齢でした。
先生のご遺志によって一般向けの葬儀等は行われませんでした。いわゆる偲ぶ会やお別れ会も固辞されておられましたが、家族同然のお付き合いをされてきた平良木ゼミ第1期生の先輩方や、愛弟子のフィリップ・オステン教授らを中心に、先生の月命日にもあたる6月8日、これまでのゼミ同窓会・OBOG会を拡張した「大平良木会」という形で、先生所縁の皆さまが集まる機会を作ってくださいました。仲間たちが集まり、旧交を温め、また新しいつながりをつくる。毎年行われてきた会と同じスタイルでした。立食形式のホールの中心には、いまでも先生がおられて談笑されているかのように錯覚してしまうほどでした。いや、きっと会場におられいつも通りワインを片手に微笑んでおられたことでしょう。
私は100名以上の法曹(司法試験合格者)を世に送り出した慶應義塾大学法学部の「平良木研究会」のいちゼミ生にすぎませんが、先生との僅かな接点についてお話をさせていただき、先生への追悼の言葉とさせていただきたいと思います。
先生との出会いはもちろん慶應義塾大学。1年生の刑法の講義です。そのときはゼミ生になるとは思っていませんでしたから、数多くおられる教授陣の一人という認識でした。3年生になるにあたり、司法試験の受験勉強をしていた私は、試験に強いという触れ込みのあった平良木ゼミの入ゼミ選抜を受け、なんとか合格することができました。まさに恩師としての平良木先生との改めての出会いです。
新3年生となったゼミ生たちとともに先生のご自宅へうかがい、奥様の美味しい料理と、文字通り浴びるようにドイツワインを飲んだことは、平良木先生の教え子たち共通の思い出です。そこには今では押しも押されぬ慶應義塾大学の屋台骨となった大教授、フィリップ・オステン(敢えて「オステン」と呼び捨てにします)も一緒でした。オステンは私たち平良木9期生にとっては同じ時期に先生に学んだ同期生なのです。
卒業した年に幸運にも司法試験に受かった私は、仲間たちと平良木先生のご自宅に報告に。奥様の美味しい料理と、やはり記憶がとぶほどドイツワインを飲みました。私は先生が好きな日本酒「浦霞」の大吟醸を実家から持っていきました。「有言実行だな」と先生に合格の労をねぎらっていただいたことを覚えています。私が卒業のときに「ぜったい今年は合格して、先生の好きな日本酒をもってまたご自宅に行きます」と啖呵をきったことを覚えていてくださったのです。
そこから司法修習を経て弁護士となり、結婚式には主賓としてご挨拶をいただきました(すでに弁護士なので当然法律事務所のボスに主賓挨拶をお願いしたのですが、平良木先生もお招きすると言ったら、がんとして挨拶は平良木先生に先にしてもらえと言われてしまったのです)。学生の時や合格のときの私の発言などを覚えていただいており感激しました。
さらに時はながれ、2011年の東日本大震災のあと、私は生まれて初めて法律専門誌に簡単な記事を寄稿する機会を得ました。東日本大震災のリーガルニーズを速報で紹介する論文です。そのとき、ふと平良木先生にこの論文を見てほしいと思い立ち(これは本当になんでそんな思いになったのか今でもよく思い出せません)、当時は大東文化大学法科大学院の委員長になっていた先生のお部屋を訪ねました。論文をみるなり先生はこうおしゃいました。
今から言う人物に会ってみるとよい。
紹介してくれるのかと思ったのですが、紹介はしてくれませんでした(笑)。道は示すから、あとは勝手に会いに行けということです。なんとも先生らしいご指導でありました。当時32歳のペーペーのわたしが途方に暮れたことは言うまでもないでしょう。それでも一念発起し、私は先生から御示唆をいただいた、慶應義塾大学のある教授に初めて連絡を取り、1通しかない論文を持参して、無茶なお願いをしました。
「災害復興法学」を作りたい。
北居功先生は、はじめて会う私の話の趣旨をよく理解してくださいました。2012年に災害復興法学がロースクールでスタート。2013年には法学部でも前期後期のフルバージョンでスタート。今では7つの大学でフル講義を展開する「災害復興法学」講座の基礎が誕生したのです。
災害復興法学の誕生を平良木先生にご報告すべく、北居先生とともに、改めて平良木先生のご自宅へ。奥様の美味しいごはん、そして北居先生ですらふらつき、私はどうやって帰宅したか覚えていないほどドイツワインを飲みました。これが先生のご自宅を訪問した最期になりました。2012年の夏の話です。
その後も、少し間があくことはあっても、基本的に毎年ゼミのOBOG会は開催され、先生と奥様にお会いしてきました。法科大学院懇親会にも初代ロースクール委員長・名誉教授として顔を出していただいており、同期ゼミ生のなかでは、比較的先生にお会いする機会は多かったほうだと勝手に思っています。
誰もが今年も元気に年を重ねられ、またゼミのOBOG会でお会いできるものだと思っておりました。2024年2月のゼミOBOG会での写真が先生と一緒の最期の写真となってしまいました。この少し後に開催された慶應義塾大学法科大学院の懇親会で交わした会話が、先生との最期の会話になってしまいました。「じゃ、がんばって」とおっしゃっていただいたと記憶しています。
先生がいなければ司法試験は合格していないだろうし、先生がいなければ札幌修習は選んでいなかっただろうし、先生がいなければ災害復興法学は生まれていませんでした。先生にはオステンやゼミの先輩方など、学者・研究者としての立派なお弟子さんがたくさんおられます。先生ご本人は私だけに特別の思い入れはないはずです。先生と関わるすべての教え子たちに等しく厳しく思いやりをを持って接してこられました。それでも私にとって、平良木先生は恩師と呼べる唯一の先生であり、人生の恩人です。これからもずっとそうあり続けるでしょう。
どうか安らかに。
平良木研究会9期生 岡本正